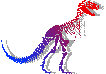 |
�����z�� |
�i�㕔�� �C���f�b�N�X������܂��B�܂����E�̕��������₷�����āC���ǂ݂��������j
��A�z�̎n�܂�c�c��
��P�b�@�w���������x
���m���o����Ԃ́A�Y��ȍ��m�p������Ɍ��Đi�݁A�₪�Ďl���œ�[�̉w�Ɋ��荞�ށB�����ɑ������ւƒʂ���l���R���̒�������B�����т��ė�����́A���{�L���̒����Ɛ������ւ��́A�l���\��i���܂�Ƃ���j�B��Ղ̖ڂ̂悤�ɐ��R�Ƌ��ꂽ�����݂́A�y���̏����s�ƌĂԂɂӂ��킵���B���̒��̖��́A�����s�B
�u�����̉���A�݂�Ȃ���������ȁB�v�u���[�Ƃ܂��A�֓��Ɣ��������Ă��܂��v�u����ł͂��߂��ȁB���Ԃ����Ă邪�����҂Ƃ����v
�u�������A�������o�Ă��邱�Ƃ����A��Ɏn�߂܂��v
�u�������ȁB��l���炢�Ȃ��ɂ�낤���B���ꂶ��܂��P��ڂ̊��t�v
��≃�����݉��ȂǂŁA�x��ė����l��҂����ɒ荏�ǂ���n�߂邱�Ƃ��A���̂����̔��˒n�����s�̖����Ƃ��āu���������v�Ƃ���(�����s�͎s���������ɂ�茻�ݎl���\�s�ƂȂ��Ă���j�B
�����݉��Ƃ����c�c��
��Q�b�@�w���ˁx
���������܂蓾�ӂłȂ����́A����i�߂���Ǝ��̂悤�ɓ����Ă��킷���Ƃɂ��Ă���B
�u�̂���̌��ɂ���悤�ɁA�w���˂ɂ��͂�x�v
�����ł́A�������߂ɍs���A�r���Ŕ����o���₷���ʒu�������Ɋm�ۂ���B���̏ꏊ�͑�̒���w�ɂ��Ă���B�����ŁA�����Ƃ����Ɖ��ւƗU��ꂽ�炱�������邱�Ƃɂ��Ă���B
�u�y���݂́A���ɒ��O�Ɏ��A���E�ɏ��A�ӂƂ�������v
�Ⴈ���Ƃ����c�c��
��R�b�@�w�n�̉��̔��x
�w������̂��Ƃł���B�S�������̕����̕ǂɁA�����Ȕ����|���Ă������B����ŏ���C�̂Ȃ����̔��ɂ́A�u�n�̉��̔��v�Ə�����Ă����B�n�̉��Ƃ͕����Ȃ�Ȃ����t�ł��������A�����ɂ��Ɓu�����D�ꂽ�����������Ƃ���A�]���ĎЉ�̕��s��h�����̂̈ӂŐ����̌��t�v�Ƃ������B
���̔��ɂ́A����Ɂu�������l�́A���R�ɂ��̒��̂��������������������B�]�T�̂���l�͓���Ă��������v�Ƃ�������|�̃��b�Z�[�W���������B
���̓d�C�n�̍u����S�����邨�����������A����Ȑl�ԓI�Ȉ�ʂ��������̂��ƌ������v���ł������B�����Ă��̂��Ƃ́A�n�̉��Ƃ������t���L�����������ŁA�����Y��Ă����B
�Ƃ��낪�ŋ߁A���̌Â��L�����v���o�����Ƃ��������B�V���ɂ��ƁA�S���e�n�ɒu����Ă������������̂��߂́u�n�̉��̔��v�����X�ɔp�~����A�Ő����V�O�O�ȏ゠�������̂��A���ɍŌ�̂R�ɂȂ����Ƃ����B
�搶�̔����A���̂����̈�ł������̂��B�����ł��������䂪�Ƃ̃��r���O�ɂ��A�u�Ƒ��Œn�̉��̔��v��ݒu�����B�����ɂ͂�͂�A�u�����ɍ������l�͎��R�ɂ���肭�������v�Ɩn�����A�~�Ə��K����ꂽ�B
�������A�䂪�Ƃł͖��ʎg�����l�̖����A�����������h�����̌�������o������ŁA����ɕs�K�Ȑl�̂��߂ɒ��܂��Ă���l�q�͂Ȃ��B���S�������������悤�ɂȂ�A�{���̒n�̉��̔��ɂȂ�Ǝv���Ă���̂����c�c�c�B
�i�ؗF�����Ў�ɓ엢���̕�ɂ��A�n�̉��̔��̉^���́A���l�ł������]���`�ꎁ�ɂ���ď��a�R�P�N�Ɏn�߂�ꂽ�B�}�^�C�`�́u���Ȃ������́A�n�̉��ł���B�������̂����߂��Ȃ��Ȃ�����A�Ȃɂɂ���Ă��̖����Ƃ�߂���悤���c�c�c�v���疽������A�����̈��̎��H�̂��߁A��������e�n�̉w��ɉ؊X�ɐݒu���ꂽ�Ƃ����B���ɂ͌����Ȃ��A�������l�₨���̂Ȃ��Ȃ������͎��R�Ɏ����A���Ă悩�����B����ŋ~��ꂽ�l�������Ƃ����A�P�ӂ̗ւ̃V���{���ƂȂ����B�j
���q���Ƃ����c�c��
��S�b�@�w�����̊G���̂P�x
�u�����v�́A���Ǝ��̍����ł��������S�O�����قǂ̉~���`�������Ñ�̏��ł���B���ꂽ���͋��F�ɋP���Ă����Ƒz������邪�A�n�����甭���������̂̓��N�V���E�𐁂��ėΐF�����Ă���B
�E���𒆐S�ɏo�y���A���݂܂łɂS�R�O�]�肪�������Ă���B�U�U�W�N�ߍ]�J�s�Ō������ꂽ�������i�����ӂ����j�������ɂ��������ꂽ���A�����ł����ł��邩�����炸�A��������`�����r�₦�Ă����炵���B
���������̂Ɏg��ꂽ���^���o�y���Ă��č��Y�ł��邱�Ƃ͊m���ł��邪�A����ړI�Ȃǂ͕������Ă��Ȃ��B�퐶�����ʂ��č���`�����ꂽ���A�퐶�����ɂȂ��ĂȂ����l�����ꂽ�R���[���������ꂽ�B
�����̕\�ʂɂ́A���R�Ƃ����w�͗l���������肳��Ă���B�m���̒���U���Ɏ���g�U���F��i�����������j�h�␅�̗����l�q��}�ĉ������g������h�Ȃǂł���B
�����Ĉꕔ�̓����i���m�ɂ͍ŋ߉��Ί�q��Ղ��甭�����ꂽ���̂��܂߂U�O���j�ɂ́A�u�Ñ�̊G��v��������B�`���ꂽ���̂́A�V�J�E�T�M�E���E�C�m�V�V�E�l�ȂǂŁA�����Ȃ��炩����E�X�b�|���Ƃ��������������A�C�����E�w�r�E��x�Ȃǂ̐��ӂɏZ�ޏ������A�J�}�L���E�N���Ƃ����������A�܂��q�ɁE�D�Ȃǂ�����B
�Ƃ���ŁA���ŕ`���ꂽ�����S�Ă̊G�́A�Ȃ������̏�Ȃ�����ł���B������Ƃ₻���Ƃ́g�G���s�h�ł͂Ȃ��A�؋�����̒t�ق��ł���B
�Ⴆ�A�l�͊ȒP�Ȑ��{�̐��ōr���ۂ��`����Ă��邵�A�V�J���葫���Ȃǂ̌`���A���o�����X�ł���B�����������͖퐶����S�O�O�N�Ԃ�ʂ��č�葱����ꂽ���A�ǂ̎���̂��̂������悤�ɒt�قŁA���̉��肳�����𒉎��ɉ�����`���������Ă���B
�������̂��̂͌|�p�I�Ő������ꂽ�`�ł��邪�A�����ɕ`���ꂽ�G�͂����ł͂Ȃ��A���̍�������Z�p�Ƒ傫�������Ă���B
�����̊G�̗c�t���́A������̑��̈╨�ł��݂���B�Ⴆ�Ζ퐶�y��̒��ɂ́A�l��D�⍂���������Ȃǂ̊G���`���ꂽ���̂�����B�Ƃ��낪�������A�����̊G�ɗւ������Ă܂����B����ɌÕ��̕lj�A�Ⴆ�Α��{�̍���c�����Õ��̌�����A���ɂ͐����Ől��D�═��ȂǑ����̊G���`����Ă��邪�A���̂ǂ�����܂��S�����܂��Ȃ��B
����|�p�I�Ŏʎ��I�ȊG������B�Ⴆ�P���U��N�O�̋��Ί펞�����̈�ՂƂ�����X�y�C���̃A���^�~����t�����X�̃��X�R�[��t�H���E�h�E�S�[���̓��A�ɕ`���ꂽ�G�́A�싍�E�C�m�V�V�E�n�E�V�J�E�}�����X�Ȃǂ̖�������p���ʎ��I�ɁA�_�`�@��F�ʂŔZ�W������A�e�@�ȂǂŌ����ɕ\������Ă���B�܂��Ñ�G�W�v�g��M���V���ł́A�|�p���̍��荂���G�⒤�����������ꂽ�B
�܂��A�R���オ��ɂ��͂���Ή����ƌĂ��������ꕶ�i��j���y��A�n�⎭��l�Ȃǂ����A���ɖ͍����ꂽ�`�ۏ��ւȂǂ�����B
���̂悤�ɓ�������̑O�ɂ́A�|�p�������ʎ����ɕx��i���������������B�ɂ�������炸�A������퐶�y��ɕ`���ꂽ�G�݂̂��ЂƂ�A���̃��x���Ȃ̂ł���B�Ñ�ɂ������|�p�����Ȃ��`������Ȃ������̂ł��낤���B�܂������̐���҂́A�����Ƃ܂��ȊG���`���Ȃ������̂ł��낤���B
���̐��_�ɑ��āA�����̌����҂͎��̂悤�ɔ��_����B���Ȃ킿�����́A�G�ȂǕ`�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B���̂��߁A���̗��K�����邱�ƂȂ��`�����̂ł����Ȃ��Ă��܂����̂��ƁB
�������A���̌������������Ɍ�����B�u�n�ʂȂǂɊG��`�����Ƃ��Ȃ������̂��v�u�����̒��Ɉ�l���G�S�̂���G�˂����Ȃ������̂��v�u�S�O�O�N���p�����ĕ`���������̂Ȃ�A�K�n����ǂ��������̂ł́v�u�V�J��T�M�Ȃǂ́A�ǂ��ɂł����铮���ł�������Ďʎ��I�ɕ`�����̂ł́v�u�����Ƃ������M�d�Ȃ��̂Ȃ�����Ƃ��܂��G��`�����Ƃ��l�����̂ł́v�Ȃǂł���B�����̋Z�p�҂܂������Ƃ��G�S�̂��鐻��҂Ȃ�A�܂����N�����\�N����葱�����̂Ȃ�A�������������Ɏ����G���`�����͂��ł���B
���́A���̓�ɂ��Č���I�ȓ�����m���Ă���B������A���̘b���̒��Ŗ��炩�ɂ���B
�Ⴓ��ɑ����c�c��
��T�b�@�w�����̊G���̂Q�x
�u�����ɕ`���ꂽ�G�̂ǂ����t�قȂ̂��v�A�����c���̊G�Ɣ�r���邱�ƂŖ��m�ɂ��錤�����i�߂��Ă���B�������j���������ق̍����^����t���G�������A�c���挤���҂Ȃǂ̋��͂čs���Ă�����̂ŁA���̋�����������Љ��B
��ʂɂT���炢�̗c���Ɏ��R�ɊG��`������ƁA��������I�ȍ\�}�ƂȂ�B����͑����̗c���ɋ��ʂ̓����ł��邪�A���l�ɂ͂قƂ�ǂȂ��B�w�K�ɂ��Ȃ��{�\�ŕ`�����悤�ɂ݂��A����́u���n�I�v�Łu���ٓI�v�ł���B
���n�I�ȓ_�ł́A�@������ɕ��ׂ�@�A�d�Ȃ�̂Ȃ��G�ɂ���@�B��ʂ̒��ɑS�i������@�C���ɍL���ĕ`���Ȃǂł���B
�@�́A��ʂɐ����������������̏�ɕ`�����̂���ׂ���ł���B�A�́A�o�ꂷ����̂��d�Ȃ�Ȃ��S�Ă�������`�����ł���B�B�́A�����Ȃǂ̈ꕔ����ʊO�ɏo���ĕ`���̂ł͂Ȃ��S������ʓ��ɓ����Ƃ��������@�ł���B�C�́A�S�̂̍\�}���l���ăo�����X�悭�`���̂ł͂Ȃ����ɔz�u���邱�Ƃł���B�����͌��n�I�ő�炩�A���������ƒP�ɉ���Ȃ����̕`�����ł���B
���ɓ��قȋK�����ł��邪�A�D�S�̂�����̂�傫���`���@�E�����_�̊G�ɂ���@�F�����_�̊G�Ƃ���@�G�W�J�}��`���Ȃǂ�����B
�D�́A��ʑ̂������ɔ�Ⴕ�ăo�����X�悭�`���̂ł͂Ȃ��A�S�̂�����̂����𒆐S�ɑ傫���`�����ł���B�E�́A�ʐ��Ȃǂł͈�̎��_�ł��邪�Ώە��ɂ���Ċe�p�x���Ⴆ����@�ł���B�F�́A�قȂ鎞�Ԃ̏o�������ꏏ�ɂ��ē�����ʏ�ɒu�������ł���B�G�́A�@�B�̐v�ȂǂŎg���W�J�}�̂悤�ɊJ������Ԃŕ`�����@�ł���B���I�ȕ`��Ƃ������邪�A�P�ɗc�t�Ȃ����Ƃ�������B
����猴�n�I�œ��قȊG���A�������͕��ʕ`���Ȃ��B�P�ɉ���Ȃ����̊G�ł���̂ŁA���܂��Ȃ낤�ƐS������l�́A����炩�班���ł��������悤�w�͂���B��O�́A����̑O�q��Ƃ������Ď��݂邭�炢�ł��낤���B�s�J�\�̊G�Ɍ�����A�S�̂�����̂�傫���`���⑽���_�⑽���_�̊G�Ȃǂ�����ł���B�������A�V�˃s�J�\�̂悤�Ɏʎ��I�ȊG�̋��ɂƂ��ĒB���ł������n�łȂ����Ƃ͖����ł���B
�܂��A�����̊G�͎��́g�G�����h�Ŋȗ������ĕ`�������ʂƂ����߂ł��邪�A����ɂ��Ă͕����������ȉ߂��邵�A�����S���̓����͐����ł��Ȃ��B
���ǁA�����̊G�̒t�ق��̓�͐[�܂����ŁA�Ñ�l�̈Ӑ}�͈Â��ł̒��ɕ����߂�ꂽ�܂܂Ȃ̂ł���B
�i���́A���̓���Ȃ������ł������I�Ȏ��̊w�������̂ɂ����B�u�́X�A�������q���ォ��k������A��l�̎q���������B�ނ͋��R�����������ɁA�V�J�⋛�̊G�������ł������珑�����Ė��ߖ߂������A��������đ呛�����Ă����l�B�����Ă���͖������Ǝv�����B�����ŁA�������璇�Ԃ������ē����������ẮA�t�قňӖ��s�����G��`���Ă������B�����B�̊G�������㐢�̊w�ҘA���A����Ђ˂�l�����ގp��z�����Ȃ���c�c�c�B�₪�Ă��̕��K�́A�q�������̔閧�̂����Ƃ��đS���ɍL�܂��Ă������v�j
���G�Ƃ����c�c��
��U�b�@�w�܂�ŊG�̂悤�x
�u��������̌i�F�͌������ˁB���Ɍ�����̂��@�N���̎O�d�̓��A�E���@�֎��̓��A�����Đ^���@�����̌d�̓��A�O����������̒��ɕ��ї����āA�g�܂�ŊG�h�̂悤���ˁv
�u���̊G�͂��܂��`���Ă��܂��ˁB���ɂ���̂����T�R�A���������R�A�����ĉE���V�̍��v�R�ł��ˁB�H�̓������ɂ������ޑ�a�O�R�����I�ɔ������`���Ă��āA�g�܂�Ŗ{���h�����Ă���悤�ł��ˁv
�l�͔��������i�����Ă܂�ŊG�̂悤���Ƃ����A�悭�`�����G���O�ɂ܂�Ŗ{���̂悤���Ƃ����B�M�����Ȃ��̌������āg�܂�Ō��h�̂悤�������Ƃ����A���������f�������āg���ۂɂ������h�悤���Ƃ����B
���f���Ƃ����c�c��
��V�b�@�w���f��x
�̂́u�Â��f��v������ƁA�l�╨���ُ�ɑ��������Ă���B�l�͂��������Ƒ����ŕ������A�H��œ����l�͂������X�s�[�h�Ŏd�������Ă���B�����k���l�̌L�̑����͋@�֏e�̂悤�����A�����Ԃ͂܂�ŃA�N���o�b�g�̂悤�ɓ��H�𑖂���B
����ȖZ�����f����A�̂̐l�͕s���R�Ǝv�킸�����̂ł��낤���B
���͂��鎞���Ɂu�̂̉f��͑��������̂��v�ƕ����Ă݂��B�����́A����Ȃ��Ƃ������Ȃ������Ƃ̂��Ƃł������B����ł́A��̍�����f��̑����͉��Ȃ̂ł��낤�B
����́A���������u�̂̉f������Ă���v�ƁA���o���Ă��邱�Ƃɂ���B�������́A�������́u�̂̉f����e���r�Ō��Ă���v�̂ł���B�悭�l���Ă݂�ƁA�����̂̉f��ځA�Ⴆ�Ήf��ق�f�ʋ@�ʼnf���Č������Ƃ͂Ȃ��͂��ł���B�������͑S�āA�e���r�̃u���E���ǂ�ʂ��Đ̂̉f������Ă����̂ł���B
�e���r�͂P�b�ԂɂR�O���̐Î~��ʂ𑗂邪�A���ꂪ�A�����Ă��邽�ߐl�ɂ͓����Ă���悤�Ɍ�����B
����Â��f��̏ꍇ�́A�P�b�ԂɂP�W����Q�S���̐Î~���A�������ē����������Ă���B���̖����́g�R�}���h�ƌĂ�邪�A�̂̉f������݂̃e���r�ł͉f���ɂ́A���̃R�}�������킷�K�v������B�P�b�ԂQ�S�R�}�ŎB�����f��́A�e���r�̂R�O�R�}�ɍ��킷���߂��ƂU�R�}����lj�����B���Ȃ킿�f��̂P�D�Q�T�b���𑁉��ĂP�b�Ɏ��߂�K�v������B���̌��ʃe���r�Ō���̂̉f��́A���̕����������Č�����̂ł���B
�u���̂��Ƃ͌������ƑS�Ă������ł͂Ȃ��A�^���͕ʂɂ���v�ƌÐl�͊Ŕj�������A���̐̂̉f��ɂ��Ă��������Ă���̂ł��낤�B
���R�}�Ƃ����c�c��
��W�b �w���疜�~���x
���ăR���s���[�^�̃}�[�P�e�B���O�̎d�����������Ƃ�����B�J�^���O�E�L���E�V�����\�E�C�x���g�E�����E�c�l�i�_�C���N�g���[���j�E�W����Ȃǂ���悵������{����d���ł���B
�W����ł́A�z�e���ȂǂŃv���C�x�[�g�V���E������ꍇ�����������A�c�̂�Вc�@�l����Â���V���E�֏o�W�����Ƃ����������B�V���E�͑S���ő召���킹�ĔN�������J�Â���Ă��邪�A�K�͂̑傫�Ȃ��̂ƂȂ�Ɛl�̏W�܂�₷���t�H�ɏW�����Ă���B��������̍`�p�����Ēn�ɍ��ꂽ�L����ݓW����ł̊J�Âł́A���P�O�O�Ђ��o�W�����K�͂Ȃ��̂������B
�傫�ȃR�}�i���ꂽ�X�y�[�X�j�ł̏o�W�ɂ́A���z�̔�p���K�v�ł���B��Î҂Ɏx�����o�W���A����Ǝ҂ւ̃R�}������A����Ƀi���[�^�[��ւ̐l����Ȃǂł���B���ł����z�Ȃ̂��A�R�}���Ɍ��Ƃ������������鑕����ŁA����͒ʏ탍�[���X���C�X���������������z�ł���B
�Ƃ��낪�V���E���̂͒����Ă��S�`�T���ŏI�邽�߁A�݉c�����R�}���킸���Ȋ��ԂŎ����ƂɂȂ�B����͔���������̐���̃��[���X���C�X���A������ɉ̂Ɠ����ł���B�ŏI���A��J���č�����R�}����ۂ悭���������\�ɉ�̂��Ă�����������Ă���ƁA���ۂ���Ȍ��z���łĂ���B
���̑傢�Ȃ閳�ʂɑ��A�����Ǝ҂Ɉ�x��������̂��Ȃ�Ƃ��ė��p�ł��Ȃ���������������B�������₽���f��ꂽ�B�����炩�猩��Ζ��ʂȎU���ł����Ă��A�ނ�ɂƂ��Ă͔т̎�ƂȂ��ȘQ��ł��邩��ł���B
�l���Ă݂�ƁA�������������ɂ��ĐV�������̔���Ȃ��ł��邱�Ƃ́A���[�J�[�ɂƂ��Ă͍�������̂����ꂾ������Ȃ����Ƃł���B���ɓW����̂悤�ɁA�I��ΑS�Ă�j��傢�Ȃ閳�ʂ��A�V���̋����Ƃ����ϓ_�ōl����Ό��\���̒��̖��ɗ����Ă��邩������Ȃ��A�Ɖ�䂭�R�}�����Ė���v�������̂ł���B
���[���ł��Ȃ��Ƃ����c�c��
��X�b�@�w���a���Ȃ����t�x
�P���g�ݍ����ĕ��͂���鎞�A��a���̂��镶�߂��i�t���[�Y�j�ɂȂ邱�Ƃ�����B�Ⴆ�u���̃f�[�^�[�͐r��Ȃ��߁c�c�v���s���R�Ɋ�����̂́A�f�[�^�[�Ɛr��Ƃ����P�ꂪ���a���Ȃ����߂ł���B�������r����P�ǂ݂��āu���̃f�[�^�[�͐r���傫�����߁c�c�c�v�Ƃ���ƁA������̕��͒��a���Ƃ�s���R�ł͂Ȃ��Ȃ�B
���͂���鎞�́A���a�̂Ƃ��P���g�ݍ�����Ƃ����̂��A���͗͌���̊�{�ł���B
���������̗��������āA���ʎg��Ȃ��P�ꓯ�m��g�ݍ�����C���p�N�g�̂���t���[�Y������B�^�C�g����L���R�s�[�ȂǂɌ�������e�N�j�b�N�ł��邪�A���̕��@�ō��ꂽ����B
�Ⴆ�u�����̏�̃��B�I�����e���v�ł́A���ʃ��B�I�����e���Ɖ����Ƃ̊W�͍l�����Ȃ����A���̈�a���̂���Q��g�ݍ����邱�Ƃň�ۂ̋����^�C�g���ɂȂ��Ă���B
�u���̉��ɂ͎��̂����܂��Ă���v�ł́A���Ǝ��̂Ƃ��������Ȃ��̂����킹�ăC���p�N�g����\���ɂȂ��Ă���B�u�ؓ������сv��u�S�������v�Ȃǂ����l�ŁA�s�v�c�ȕ������B
�s�̃R���e�X�g�ւ̉�����Ăт�����u�s���̏h��v�Ƃ����L���b�`�R�s�[���A��a�����������邱�ƂŌ��ʂ������Ă���B�������A�ȏ�͌��t��P�Ƀ����_���ɑg�ݍ������Ƃ��������ł͂Ȃ��A���Ԃ܂��Ă̕\���ł���B
����ɁA���j��̎����ł͂��ꂪ���������ꏊ�i�Ⴆ�u�{�\���̕ρv��u�ԕǂ̐킢�v�j�A�N���i�u�p�\�̗��v��u���m�̗��v�j�A���i�u�����\���������v��u���Ђ̗��v�j�A�l�i�u�V��V�����v��u�剖�����Y�̗��v�j�Ȃǂ��������ꍇ�������B�������A�������������������̂܂ܖ��̂ɂ����u�Q�Q�U�����v�u�T�P�T�����v�u�O���v���v�Ȃǂ��A�l�[�~���O�Ƃ��Ă͈�a���������Ȃ�����Ԃ���ꂽ�悢�A�C�f�A�ł���Ƃ������B
�������Ƃ����P�c�c��
��P�O�b �w�L�O���x
���i���ʂɒ����̔�����ɂ́A�l�X�̐����K���ɑg�ݓ���邱�Ƃ��L���ł���B�u���������ɂ͂��̏��i���K�v�v�u�������������ꂪ�~�����Ȃ�v�u���̏ꍇ���ꂪ�s���v�Ȃǂł���B
���̓T�^���A�J�����_�[�ƘA�����Ă��̂�Ƃ�����ł���B�u���̓��ɂ͂�����g���v�u���̋L�O���ɂ͂�����v�Ȃǂł���B
���̓��́A�����̌�C�Ō��߂�ꍇ�������B�Ⴆ�A�P���S���͂P�S���C�V�Ɠǂ�Łu�̓��v�A�Q���P�O���́u�j�b�g�̓��v�ł���Ɠ����Ɂu�ӂ��̂Ƃ��̓��v�A�T���Q�X���́u�����̓��v�Ɓu����ɂႭ�̓��v�A�P�O���X���u�g���b�N�̓��v�Ɓu�m�̓��v�Ȃǂł���B
�܂��A�������̂悤�ɏ����l������ŕ�������̂�����B
�Ⴆ�P���W���́u�����̓��v�ł��邪�A����́g�ꂩ�����h���炫�Ă���i�C�`�J�o�`�J�́g�ꂩ�����h�ŁA�T�C�R���q���ňꂪ�o�邩�������邩�̈ӂƂ�����j�B�S���P�O���́u�w�ق̓��v�ŁA�w�ق̕ق̎����S�Ə\��g�ݍ��킹�̂Ɏ��Ă��邱�Ƃɂ��B�V���V���́u�S�����ʂ̓��v�ł��邪�A���ʂ̒��������������i��Q�R�����j�ł��邱�Ƃɂ��B�W���P�O���́u�X�q�̓��v�ł��邪�A�p��̃n�b�g�𐔎��̌�C���킹�łW�P�O�ł��邱�Ƃ��猈�߂�ꂽ�B�P�P���P�W���́u�y�̓��v�ł��邪�A�y�Ɩ�����Ώ\��Ə\���ɕ�����邱�Ƃɂ��B�P�O���W���́u�̓��v�Ɓu���Ɗ߂̓��v�ł��邪�A�⍜�̃z���\�Ɣ��ɕ����邱�ƂŖ��t�����Ă���B�P�O���P�O���́u�ڂ̈���f�[�v�ł��邪�A���т��g�P�h�ڂ��g�O�h�Ƃ��āA����łP�O�P�O���炫�Ă���B�P�P���Q�T���́u�n�C�r�W�����̓��v�Ńn�C�r�W������ʂ̑������i�摜��`�����߂ɉ��ɑ���u���E���Ǐ�̐��j���P�P�Q�T�{�ł��邱�Ƃɂ��B
�܂��A�������肱��܂����������g�ˌ������h�̂悤�ȋL�O��������B
�����P�Q���͌�C���킹�Łu�����̓��v�A�P�T���́u�������̓��v�A�P�W���́u�����̓��v�A�P�X���́u�g�[�N�̓��i�b���j�v�A�Q�Q���́u�v�w�̓��v�A�Q�R���́u�ӂ݂̓��v�Ɓu�{���̓��v �A�Q�U���́u�ӂ�̓��v�A�Q�W���́u�j���g���̓��v�A�Q�X���́u���̓��v�ł���B
���̂悤�ɁA���ꂼ��̋L�O���͎�ɐ����̌�C���킹�Ō��߂��邪�A�����ɂ��̓��ɓ���̏��i���v���o�������Ă��������Ƃ̋Ǝ҂̉���ȁg�A�d�h���܂܂�Ă�����̂�����B�H�ו��̗�ł݂�B
�P���P���͂������Ƃ������������̉A�d�ł���B�Q���R���͓����̉A�d�łЂ���Ƃ����瓤�������גS���Ă��邩������Ȃ��B�Q���P�S���Ƀ`���R���[�g�𑗂�͓̂��{�����̕��K�Ŗ��炩�Ƀ`���R���[�g���̂�����݂ŁA����ɑ���R���P�S���z���C�g�f�[�̃L�����f�[����}�V���}���Ǝ҂Ƃ��ł���̂�������Ȃ��B�R���R���͂���ꉮ��Î�����H�݉��Ȃǂ̏W�c�����ł���B
�R���Q�P���̂ڂ������ƂX���Q�R�����͂��i�������̂��A�ڂ��炭���Ɣ����J�����ɍ��킹�ČĂі���ς��Ă���̂������ł���j�͋��ɂ����̃_�u���̛@��ŁA�������Ə��������㉟�����Ă��邩������Ȃ��B�����͂܂��A�T���T���̔��݂�X���P�U���i����W���P�T���j�̒��H�̖����̌����c�q�����A�ő����Ă���Ɗm�M�ł���B
�P�P���P�T���̎��O�̐�Έ��̓A�����̌��d�Ő_�Ђ�����Ă���ɈႢ�Ȃ����A�P�Q���Q�T���͉������Ăُ̈@���Ƌ��d���ẴP�[�L���̂͂��育�Ƃł���A�P�Q���R�P���̔N�z�����͂��Ή��̌v���Œ��쌧�����Ŏ��������Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�i�������̑s��Ȃ�A�d�ɋC�Â����̂́A�ŋߐ���Ɍ��`���������Q���R���ߕ��̓��̌b���Ɍ������Ă̂芪���ۂ��Ԃ�Ƃ������i���̃L�����y�[����m���Ă���ł���B�j
�Ⴓ��������Ƃ����c�c��
��P�P�b�@�w���I�Ƃ����\���x
���j��̔N��́A�u���I�v���g���ĕ\������ꍇ�������B�Ⴆ�Ί��q���{�����͂P�Q���I���Ƃ��A�P�W���I�O���ɓ���g�@�ɂ���ċ��ۂ̉��v���s��ꂽ�Ȃǂł���B
�������A���̎���̕\���@�͒����I�ɕ�����ɂ����B
���q���{�����̂P�Q���I���͂P�P�X�Q�N�ł���A�P�Q�Ƃ�����������P�P�O�O�N���z�N����K�v�����邽�߁A�P�Q����P�������P�O�O�{���ĔN��������B
��������������j��̔N�����A�����̌�C���킹�ŋL�����Ă�����̂������B��قǂ̊��q���{�����́u�������i�P�P�X�Q�j��낤���q���{�v�ł���B���������āA���Ƃ��琢�I���g���K�v�͂Ȃ��A������P�Q���I�ƌ����Ă��P�P�O�P�N����P�Q�O�O�N�̊ԂƂ��ƂƊ��Z�������čl���Ă���B����Ȃ�A�������P�P�O�O�N��㔼�Ƃ����������̂ق�����������B
�{���ł͂��̔N��Ƃ����\����W���Ƃ��A���I�\���͕K�v�ŏ����Ɏ~�߂Ă����B
�����j�Ƃ����c�c��
��P�Q�b�@�w���j�͖{���ɂ������̂��x
�������́g���j�h���w�Z�����ʂ��Ē��������Ă����B�܂����ƌ�����j����Ƃ���l�������B
���j���w�ԂƂ́A���Ȃ킿�ߋ���m�邱�Ƃł���B�m�����ߋ��́A�����ɑ���w�j�ƂȂ�A�߂����J��Ԃ��Ȃ����߂̋��P�ƂȂ�B�̐l�̐������ɐS�ł���邵�A���j��̋�l�͔��ʋ��t�ƂȂ�B�퍑����̉p�Y�̊���ɋ���邱�Ƃ��������A�Ñ�̃��}���Ɠ�ɂ͋������s���Ȃ��B���j�ɓo�ꂷ��ꏊ��K��邱�Ƃŗ��s�̋Ђ͍L���邵�A�p���ƂȂ�����Ղɂ�������ʼn������ÂԊy���݂�����B�Z�p�j��m�邱�ƂŌ��݂̋Z�p�̏d�v���������ł��邵�A�����̐����ɗ��j��������N�����Ό��݂̈ʒu�t�������m�ɂȂ�B�������j��������邱�Ƃœ`���Ɛ��������ւ�邵�A���̔N����g���̒��ɏ�������邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ͗��j�ɐV������ނ����߂邱�Ƃ��ł��邵�A���㌀�����邱�Ƃʼnf��̃W�������͑傫���L����B
���̂悤�ɁA�������̒m���͗��j�ɂ���č��܂邵�A���̃X�e�[�^�X�����p���邱�Ƃ��ł���B
�������A���j�́g�ߋ��ɑ��݂��������h�Ȃ̂ł��낤���B���������m���Ă�����j�́A�{���ɂ��������ƂȂ̂ł��낤���B�Ђ���Ƃ�������̂̂Ȃ����̂��A�������͗��j�ƌĂ�ł���̂ł͂Ȃ��̂��낤���B���������s�����A�N�������鎞������B
���j���ߋ��ɑ��݂��������ł��邱�Ƃ��ؖ�����̂́A���͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�����������ۂɊm�F���F���ł���̂́A���ڂ̑O�ɂ��鎖�ۂ����ł���B���ԂƂƂ��ɏ������������̂́A�����Ƃ��Ă͔F���ł��Ȃ��B�����ɂȂ����̂́A�P�ɐl�̈ӎ���_�̒��ő��݂��Ă���ɉ߂��Ȃ��B�����l�X�̋L�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����A����͑��݂��Ȃ������̂Ɠ����ł���B
�V�������j�I�������Ղ���������A���ꂪ���܂ł̗��j��̒m���ƈ�v�������A�l�X�͗��j�������ł������Ɗm�F����B�܂���\��K��āA�����Ɋm���ɉ������������ƔF���ł���B�������č��܂ł̋L�����A�ߋ��Ɏ��ۂɑ��݂��Ă����̂��ƈ��S����B
��������͂肻��͔F���݂̂ŁA���j���̂��̂́u�l�̈ӎ��̒��v�ɂ������݂��Ȃ��B�S�Ă̗��j�����ł������Ƃ��Ă��A�l�͂���ɔ��_���鉽��p�������Ȃ��B���ۂɖڂ̑O�ɁA���鋞�������āA�M�������āA���H�����̐킢���Ȃ�����A�ؖ��̂��悤���Ȃ��̂ł���B�i��U�w�҂Ŕ]�̌����Œm����{�V�Ўi���́A�܊���������Ă��錻�����u�A�N�`���A���e�B�v�A���̒��ō��グ���������u���A���e�B�v�Ƌ�ʂ��Ă���B�����āA�A�N�`���A���e�B�Ȃ��Ƀ��A���e�B�̐��E�������̐��E�Ǝv�����ދ������߂Ă���B�j
����\�Ƃ����c�c��
��P�R�b�@�w�p�̓V�c�̓m�x
�Ñ�ɂ͑����̓䂪����B���̓䂪����قǂɁA�Ñ�j�͖ʔ����B
�����ē�̌Ñ�j�̒��ł��A���ɑz���̗����L����~�X�e���[�́A�הn�䍑�Ɠ�������Ɂu�p�̓V�c�v�ł��낤�B
�p�̓V�c�͑�Q�U��̐l�c�ŁA����S�T�O�N����T�R�P�N�܂Ŏ��݂����Ƃ����邪�A���̏o���ɂ͓䂪�����B
�p�̂̐��͂Q�T�㕐��V�c�ł��邪�A�L�I�i�Î��L�Ɠ��{���I�j�ɂ͂��̖��̎����Ƃ���A���\�Ŏc�E�Ȑl���Ƃ��ċL����Ă���B�u�����̍Ō�̉��@�i���イ�j���A�������\�N�Ƃ��ĕ`����A���ɂƂ��đ���ꂽ�b���ƍ�������B�����ɂ́A�f��Ɛ�����̓���������B
����ɂ͎q���Ȃ������̂ŁA�P�T�㉞�_�V�c�̖T�n�̂T�゠�Ƃ̍c���������z�i����j����T���o���A�c�ʂɂ��������ꂪ�p�̂ł���B�������T��Ƃ������̊ԂP�T�O�N�͗���Ă��āA�������咣����ɂ͖���������B
�܂��p�̂́A�s�̂���ɂQ�O�N�߂������邱�Ƃ��ł����A���̊ԌR���ƌ�ʂ̗v���ł��������여��œ_�X�ƎO�x���s��ウ���Ƃ����B�����ɂ́A����h�����͂̒�R����������B
����Ɍp�̖̂����̂ɂ��A�s���R�����c��B��ʂɓV�c�͎���A���̎��тɂ�����恁i���݂ȁj��������B�p�̂Ƃ͂܂��ɁA�V�c�Ƃ��p�����Ƃ��Ƃ��拁i������ȁj�ł���B
�ȏ�A�����E�J�s�E恂Ȃǂǂ���Ƃ��Ă��A�V�c�ƒf��̉\���͍����B���邢�́A���N�����̉e�������k���n���̐V���������ߋE�ɐi�o���A����܂ł̑剤�Ƃ�ł����������������̂�������Ȃ��B
���̂悤�ȋ^���͂P�O�㐒�_�V�c�Ȃǂɂ��݂��A������n�i���P�Q�T�㍡��V�c�܂Ō��������ĂƂ������Ɓj�ł���͂��̓V�c�Ƃ��A�����̒i�K�ɂ����ẮA���邢�͑������f�₵���̂�������Ȃ��B
�����̌p�̓V�c���A�T�O�V�N�ɑ��ʂ����ꏊ�Ƃ���鏾�t�{�i�����݂͂̂�j�Ղɗ��B�����͑��Ƌ��s�̒��ԗ���̓��݁A���������Ƃ������n�т̒��ɂ���B�ē��́A�����c��Z���K�i�����͂��j�̐��P�U�O�O�N�O�����̂܂܂Ɠ`����B
�������ÂттA���������݂��ߐΒi��o��B
���̗���͑S�Ă�Y�p�̔ޕ��ɉ������邪�A����̑O�ɂ���ؘR����Ɍ��铥�ݐ������p�̓V�c�̉�������Ă���B���������H������������Ȃ��Ái���ɂ����j�̐������A�����Ɍp�̓V�c�̐���������`���Ă���B
�����Ƃ����Ό��������x��c�c��
��P�S�b�@�w���N�T��c�x
�g���N�T��c�h�Ƃ������t�ɂ́A�����������D�Ƌ��ɁA���������x�郍�}�����܂܂�Ă���B�q���̍��T�ゲ���������ẮA���������N�T��ɂȂ������G�ɐ�������Ă����B
�����āA���̍��o�����g���N�T��c�̕��@�h������B
����́A�r���v�ŕ��p��m��Ƃ������̂ł���B���p��m��ɂ́A�܂��r���v�̒Z�j�z�ɍ��킹��B����ƂP�Q���̕������A��ƂȂ�B
���̎q���̎��o�����֗��ȕ��@�́A�����傢�ɗ��p���Ă���B
�������Ƃ����c�c��
��P�T�b�@�w���b�c�R�x
�����R�T�N�͂Q�O���I���n�܂������̔N�ł���A���V�ȗ��g�債�Ă����R�����g���đ卑���ɂ������������߁A���^�܂��܂���������N�ł������B
����e���̒鍑��`�ɏ悶�ē��{���̓y�I��S�������ɂ��A���B�i�����k����сj�⒩�N�����ł͓����i�o����Ƃ郍�V�A�ƈ�G�����̊댯�ȏ�Ԃɂ������B���ۂQ�N��ɂ͓��I�푈���u������̂ł��邪�A���̋ٔ��������R���͏������푈��z�肵���P�����J��Ԃ��Ă����B���z�G���̓��V�A�ł���A�킢�ɂȂ�V�x���A�Ȃǂ̋Ɋ��n�ł̐킢�͕K���ł������B
�����ŁA�����Ɋ���Ă��镔���Ɋ��҂����܂�A���k�̊e����������n�ł̌R���P�����J��Ԃ����B
�X�ɂ����T�A�����A�ᒆ�ł̌P���Ȃǂ��n�߂Ă����B�ᒆ�P���ł̌R���ۑ�͂�������������B����̒��ŏe�����܂����Ă邩�i��������܂������܂܂Ō��ɂ͂ǂ�����悢���j�A�����ɂȂ�Ȃ����߂̑����́i�R�C�̒����ǂ�����Γ����ɂȂ�Ȃ��ł��ނ��j�A�������ł̐H���͂ł��邩�i����т͓����Ă��܂�Ȃ����j�A��⋂͂��܂��������i��̒��H����e��������悭����ɂ́j�A��̒��ŐQ�邱�Ƃ��ł��邩�i�啔�����ᓴ�̒��Ő������Ƃ邱�Ƃ��ł��邩�j�ȂǑS�Ăɓ�����K�v���������B
�����ŐX��T�A���́A�����̑̌��̂��ߐᒆ�R���P�����v�悵���B�X���o������̔��b�c�R���o�čO�O�܂łQ�R�O�j�����P�Q���Ԃ����ē��j������̂ł������B
�R�ł͍���v��͎Q�d������A������w�����Ɏ����w���������ɖ��߂��ČR�͓����B�v��͎w�����ł͂Ȃ��A�K����헧�Ẵv���W�c�ł���Q�d�����B��T�A���ł��A���t���̎Q�d���A�Ȗ��Ȍv������グ���B�����ĘA���̒����狭���Ŋ����ɋ����Q�P�O�l��I�����A���S�̑����ŐX���o�������B���ɖ����R�T�N�P���Q�O���̂��Ƃł���B
�Ƃ��낪�A�Q�d���v�������������Ȍv��ł��������A�o�������r�[�����͓��������Ă��܂����B�����Đ�̔��b�c�R�����������A�P�P�l�����낤���ċ~�o���ꂽ���̂́A�����̑啔�������������B���̎����́A�R���͎��Ɨׂ荇�킹�ł���Ƃ͂����Љ�I�ɑ傫�Ȗ��ƂȂ����B
�����āA������̒Njy���n�܂����B���̂P���Q�O���́A���k�n����җ�Ȓ�C�����P���A�����c��}�C�i�X�S�P�x�Ƃ����L�^�I�ȍŒ�C�����k�C������Ŋϑ����ꂽ�O�X���ł��������߁A��T�A�����g���Ă��Ȃ������h�Ƃ̐��������������B
�Ƃ��낪�A���̘b���ɂ͂��܂�m���Ă��Ȃ�������ʂ̕����̘b�����������B����͂�͂蓯�����ɁA��T�A���Ƃ͑S���t�ɍO�O���甪�b�c�R��ʂ��ĐX�Ɍ����������������B�O�O�ɂ����R�P�A���̎Q�d���v�������Ď��s�������̂ŁA�K�͂͏����������������A���̕����͑�T�A���̑����K�ڂɁA�N�ЂƂ�E�����邱�ƂȂ������ɐX�ɓ������Ă����B
���������āA���͂��T�A���͉^�����������ł��܂���Ȃ����ƂɂȂ����B���ۂ��̂Q�̕����̌v����r����ƁA��T�A�����P���Ƃ������ƂŎՓ�ɓ˂��i�ދ��s�R�ł������̂ɔ�ׁA��R�P�A���̂���͐�̕|���̔F���̂��ƂɈ��S��������œ������̏Z�l�Ɏ��X�Ɠ��ē��𗊂ނ��Ƃ�A�ᒆ�s�i�͗\�z�ȏ�ɑ̗͂����Ղ��邽�ߋx�{���\���ɂƂ�Ȃǂ̑���Ƃ��Ă������Ƃ�������B
�������́A���̂Q�̎������瑽���̋��P�邱�Ƃ��ł���B�����ē����Ƀv�����̑P�����������ʂ�傫�����E���邱�ƁA���̃v���������Q�d�A��Ƃł̓X�^�b�t�̐ӔC�������ɑ傫������m�邱�Ƃ��ł���B
���푈�Ƃ����c�c��
��P�U�b�@�w�t�F�C���Z�[�t�x
���ăA�����J�ƃ\�A���A�O���╴���̏�Ŕe����������g���̎���h�������������B���̎���A�M���푈�ɂ܂ŃG�X�J���[�g���邱�Ƃ͖Ƃꂽ���̂́A�푈�J�n�������u�j�푈���v�v�͂��������O�������A�����~�X���S�ʐ��E�푈�J�n�̈������ɂȂ�\�����������B
������������w�i�̒��A�����ł�����j�푈�f�悪�������ꂽ�B���̈�ɃA�����J�f��uFail Safe�v������B���ӂ́A�g�������s���Ă��K�����S���ɂȂ�h�Ƃ������Ӗ��ŁA���̌��t�͂��̌㗬�s��ɂȂ�A�܂��Z�p����ł͍����g���Ă���i�d�Ԃ̃G�A�[�u���[�L�Ȃǂ����̗�ł���j�B
�X�g�[���[�́A�����ł���B�헪�i�ߎ������w�ɂ�������c����O�ɁA���R�͓��ӂ��ɌP���̗l�q���������B�X�N���[���ɂ́A������ςďd�����@�̋@�e���f���Ă���B���̃V�X�e���̓t�F�C���Z�[�t�̂��Ƃœ����Ă���A����̏�⎖�̂��������Ă������Ĉ������ƂɂȂ�Ȃ��Ɨ͐�����B
�₪�ČP�����I�����A�����@���i�o���Ă����n�_��������Ԃ��悤���߂��o�����A�X�N���[����̋@�e�͂ǂ�ǂ�\�A�̓y�ɐN�����Ă����B�t�F�C���Z�[�t�������Ȃ��Ȃ������Ƃ�m�������R�́A�Q�Ăđ哝�̂ɐi������B�哝�͍̂��Ƃ̈�厖�ɁA�h����z�b�g���C���Ń\�A�Ɍ��̓d�b������B
���̎����V�A��̒ʖĂ�A�哝�̂����̔C�����^������B�u�N�̎d���́A����̌��t�𐳊m�ɖ��Ƃł���B����������ȏ�ɏd�v�Ȃ��Ƃ�����B���肪���錾�t�̗��ɉB���ꂽ���A�S�̓����⊴��̕ω��𒀈�`���ė~�����v�ƁB
�哝�̂́A�����X�N���Ɍ������Ă��锚���@�̓~�X�ŁA������������Ă��U�������Ȃ��悤�ɁA����͒P�Ȃ�@�B�̌̏�ōU���̈Ӑ}�͂Ȃ��Ƒi����B����ɑ��́A���͂Ƒ��k���Ȃ�����𑱂���B
�ʖ�́A�h���̐S����u�������Ă�����U�肾�v�u���M�Ȃ��悤���v�u���S������������v�Ɠ`����B
�������A�����ɒx�������͓�������A���X�N���͈�u�ŏ�������B�đ哝�͎̂ւ̒�Ăǂ���A�����̍Ȃ�����j���[���[�N�Ɏ���̎�Ő����𗎂��B�������A�����ɕ̂��߂̃��V�A�̂h�b�a�l�͔��˂���Ă���A�Ƃ������؏����ł���B
�����ł́A�����̐��E��킪�N���肤�邱�ƁA�����ɍ���܂��t�F�C���Z�[�t�ň��S���ɐv���ꂽ���̂ł����S�łȂ����ƂȂǁA�����̋��P������B
�������A���̉f�悩��͂���Ɋw�ԂƂ��낪�������B
��́A�j���[���[�N�Ɏ���̎�Ő����𗎂����ƂɂȂ������ɊJ���ꂽ���h��c�ŁA�c�����u���̍��̏����ɂƂ��ĕs���Ŕ����˂Ȃ�Ȃ��d�v���ނ����邩�v�Ɖ��₷��Ƃ���ł���B����ƁA�o�ϊw�҂͌����Ɂu�m�[�v�Ɠ�����B�c�X�ƍ��グ�������l�ނ̕����E�Z�p�E�o�ρE�����E���j�Ȃǂ��A��ɕK�v���ƕ������ΑS�Ă����͂����ł͂Ȃ������̂ł���B
�܂��A���V�A�Ƃ̌��Œʖw�͂����\�ʂɏo�Ȃ����̎��W�ł���B����͍��̒����ł�������A�d�v�ȕ��@�ł���B
�Ȃ��A�������ɍ��ꂽ�����j�푈��`�����u���m�ُ̈�Ȉ���A�܂��͎��͔@���ɂ��ĐS�z����̂��~�߂Đ�����������悤�ɂȂ������v������ł���Ɠ����ɁA�^�C�g���̊��������������B
������������Ƃ����c�c��
��P�V�b�@�w�傫�ȗ①�Ɂx
�����m�푈���I���āA�A�����J�������ǂǂ��Ɨ��ꍞ��ł����B
���ɏՌ��I�ł������̂́A�e���r�f��ɉf���o���ꂽ�A�����J�̉ƒ땗�i�ł������B���̒��ň�ې[�������̂͐H�����ŁA����^�̗①�ɂɂ͂���Ƃ�����H�ނ��l�܂��Ă����B����̋����r�A�Ԍ����X�e�[�L���A�������s�U�A����̃A�C�X�N���[���Ȃǂ��A����ł����Ƃ��ӂ�Ă����B
����ȍ��ȐH����������A�����J�l�ɁA�G���ł��낤�����Q�������Ă������{�l�����Ă�킯���Ȃ��ƁA���̎����݂��݂ƌ�����B
���Q���Ƃ����c�c��
��P�W�b�@�w�C���t���x
�A�t���J�������A��鯂⒎�Q�ŋQ�[�ɂȂ�Ɗe�����片���̎肪�������ׂ���B�O�H�̍����{�ɏZ�ގ��������A�L��]��H���𑗂낤�Ǝv���B��������Ă���l�ɓ͂��Ċ���Ǝv���B����Ȃ����̂͑���悢�ƒP���ɍl����B�������A���͂���ȂɊȒP�ł͂Ȃ��B
����Γ͂��ƍl����̂́A�������̊��o�ł���B�����������ē͂��ɂ́A���̍��̃C���t���X�g���N�`�����Ȃ킿�Љ��Ղ��ł��ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B�H���𑗂������D������`�p���Ȃ��A���g���ł��Ă�����������ɑ���S������������Ă��Ȃ��A�n���ɑ����Ă������܂œ͂���g���b�N�̎�z�����Ȃ��Ƃ��������Ƃ�������B���̃C���t�����ǂ�����ł������Ă���ƁA�����ŕ����͎~�܂��Ă��܂��B�m���ɍ����Ă���l�ɓ͂���ɂ́A�C���t���̐������s���Ȃ̂ł���B
�����āA����Ƃ悭�����̂����W�I���v���[���g����Ƃ����b���ł���B�y����ł��炨���ƃ��W�I�𑗂�̂ł��邪�A�d�C���Ȃ��Ƃ���ł͓��R�g���Ȃ��B����ł͂Ɠd�r�����W�I�ɂ��Ă��A���d�r���w���ł��Ȃ���Ύ��p�ɂȂ�Ȃ��B�������̎���ɂ́A�d�C�͋�C�␅�Ɠ����悤�ɂ���̂ŁA���̂��ƂɋC�Â��ɂ����B
����Ȏ��A�Ȃ�قǂƂ��Ȃ�r�㍑�����̐V�^���W�I��m�����B�G�l���M�[�ɓd�C��d�r���g���̂ł͂Ȃ��A�l�W�̃G�l���M�[���g���̂ł���B�l�͂Ńl�W�������ƁA���d�ł��P���Ԉȏ�͕�����Ƃ����B
���[��A����́g�K�v�������̕�h��n�ł����A�������l�̂��߂ɂȂ鐻�i�ł������B
�i�Ȃ����̎芪�����d�����W�I�́A�h�Зp�Ƃ��č����ł����������悤�ɂȂ����B�j
�������Ƃ����c�c��
��P�X�b�@�w�G�W�\���̓d���x
�G�W�\���́A�����̔����E�����̒��ł��A�u�d���v�̊J���ɍł��S���𒍂����Ƃ�����B����͔ގ��g�̌��t�u���͓d���̂��߂ɍł����������A�܂��ł������Ȏ�����v�����ꂽ�v������m���B
�G�W�\�����J�����n�߂��P�W�O�O�N�㒆�t�ł��邪�A�����d�C�����G�l���M�[�ɕϊ�����d���͂Ȃ��͂Ȃ������B���ł��d���̌`�Ƃ��Ă��̖����Ƃǂ߂�X�����Ȃǂ��A����Ɍ��������i���o���Ă����B
�������A�t�B�������g�i�������镔���j�������Ȃǂ̋����ł��������߁A��R�l���Ⴍ�A���̂��ߑ����̓d����d���ɒ���ɐڑ�����K�v���������B����ڑ��ł́A���������ɂȂ���S����������A�܂��t�Ɉ���������悤�Ƃ��Ă��S�Ă��_�����Ă��܂����ƂɂȂ����B�܂��������̃t�B�������g�ł͎������Z���A���ǎ��p�I�Ƃ͂��������y�����Ă��Ȃ������B
���̂��߁A�X���Ƃ��Ă͂����ς�K�X��R�Ă����Ė�����Ƃ���K�X�����A�܂������ł͂܂��Ζ������v�������������Ă����B
�����������A�~�����̒~���@���J�����I�����G�W�\���́A����܂ł̓d����K�X���Ȃǂɒu�������V�������p�I�ȓd���̊J���Ɏ��g�B�܂��ނ́A�]���̓d���̌��_�����P����ɂ́A�d���ɕ���ɐڑ����邱�Ƃ��K�v�ł���ƍl�����B����ڑ��Ȃ�����Ă��A���̓d���ɉe�����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�����ŁA�ނ͒�R�l�̍����t�B�������g�̊J����ڎw���A�g�߂ɂ���ؖȎ��E�ؔ�ЁE�Ƃ����낱���̌s�E�ނ莅�Ȃǎ���̂��̂��A�S�y�ŕ��ŏ����Ă��ɂ��ĒY�������A��R�l��������v�ȑf�ނ�T�����B
�������A�����ł�����̕ǂɂԂ������B�V�����d�����̎�{�ƂȂ�̂́A���Ɏ��p����Ă����K�X���ł���B�K�X���́A��̑����p�C�v�ŃK�X�𑗂�e�ƒ�ōׂ��ǂɕ��z���āg����ڑ��h���Ă���B�Ⴆ�T�̃K�X��������ɂ́A�����p�C�v�łP�̗ʂ̃K�X�𑗂�A�e�K�X���łP�^�T�Âɕ�����Ε���ڑ��ł���B
���̃A�i���W�[�ōl����ƁA�P�̓d�C�𑗂��ēd�������_������A�P�^�T�̖��邳�ɂȂ�B�Ƃ������Ƃ́A����_������d���������Ȃ�Ȃ�قLjÂ��Ȃ�ƍl�����A����ł͎��p�ɂȂ�Ȃ������B���̍l�����́A�����c�_����Ă����G�l���M�[�ۑ��̖@����������R�̋A���ł������B
�������A�G�W�\���͓d�C���K�X�ȂǂƂ͓����Ɉ����Ȃ����Ƃ𗝘_�I�Ɏ������߂ɁA�V�����@�����g���Ă��̖����������B�I�[���̖@���ł���B
���̖@���ł́A�P�̗ʂ̓d�C�����ɐڑ������d�����ꂼ��ɑ��邱�Ƃ��ł��A����̓G�l���M�[�̖@���ɂ������Ȃ������B
�t�]�̔��z�ō���R�̃t�B�������g����邱�ƁA�����ɃI�[���̖@���𗘗p���邱�ƁA���̂Q�A�C�f�A�ŃG�W�\���͎��p�I�ȓd���̊J���ɐ��������̂ł���B�����āA�����̈ł𖾂邭�Ƃ炷���@�̋������o���A���̐��ʂ���ނ́u�������[�p�[�N�����@�g���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B
�i�Ȃ���L�ł͓d�C�Ə��������A�I�[���̖@�����g���Đ��m�ɕ\������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B�d������d���ő傫�ȓd�C�e�ʂ��������A�Ⴆ�P�O�O�{���g�d���̓d���ɂP�O�O�I�[���̒�R�l�̓d�������������ɐڑ����Ă��A�S�Ă̓d���ɂP�O�O�{���g���P�O�O�I�[�����P�A���y�A�̓d���������B����ƑS�Ă̓d���́A�P�O�O�{���g�~�P�A���y�A���P�O�O���b�g�̖��邳�œ_������B�j
�����@���Ƃ����c�c��
��Q�O�b�@�w����͉̂̓�x
�u����͂ɂقւƁ@����ʂ���킩�@�悽�ꂻ�˂Ȃ�ށ@�����̂�����܁@���ӂ����ā@��������߂݂��@���Ђ������v�́A�q���̎��������g����͉́h�ł���B���̈Ⴄ�S�V�����i�g��h�����ĂS�W�����j���g���č�������̂ŁA���Y�������ĉ̂��ƑS�Ẳ����ԒP�Ɋo������Ƃ����킯�ł���B
���������ۂ́A���̔O���̂悤�Ȍ��t�ɂ������Ƃ����Ӗ����������B
���Ȋ���������ł́A���̂悤�ɏ����B�u�F�͓��ւǎU��ʂ���A�䂪���N����Ȃ�ށA�L�ׂ̉��R�����z���āA���������Ђ������v�B�����̖��튴��\�����������̖��̂ł���B
����͉̂͒ʐ��ł͍O�@��t�i��C�j��Ƃ���邪�A���ۂ͂��̎���̕������㒆���Ɋ������ꂽ�Ƃ�����B
�Ƃ��낪�A���̉̂ɂ���g���낵����h���B����Ă��鎖����m��l�͏��Ȃ��B
����͉̂��V�����Âɕ����ď����A���̖����𑱂��ēǂ�ł݂�B����Ɓu�Ƃ��Ȃ��Ă����v�A���Ȃ킿�u�ȂȂ��Ď����v�Ɠǂ߂�ł͂Ȃ����B�ȂƂ͍߂̂��ƁA�߂��Ȃ��E���ꂽ�Ƃ����̂ł���B
�@���������Ԏ��l���A�č����炱�̉̂ɂ��̔߉^������Ĕ��M�����̂ł���B���ӎ��̂����Ɍ�������ł����̂ɂ��A���낵���䂪����ł����B
�i�Ȃ��A���̂悤�ɈقȂ�Ђ炪�Ȃ�S�Ďg�����̂́A���ɂ����邪�A����Ƃ������̂��ЂƂB�u�Ƃ�Ȃ�����@��߂��܂��@�݂悠���킽��@�Ђ����@���炢��͂��ā@�����ւɁ@�قӂ˂ނ��ʁ@����̂����i���������A���o�܂��B���斾���킽�铌���A��F�f���āA���ӂɔ��M�Q�ꂢ�ʁA�ɂ̓��j�v�B������̕��́A���낵����͊܂܂�Ă��Ȃ��悤�ł���j�@
|
����͂ɂق��� |
�������Ƃ����c�c��
��Q�P�b�@�w���薳�߁x
���薳�߂Ƃ������t������B��O���̎��ɂ́A�g����h�Ɓg���߁h�Ƃ������a���Ȃ��Q����ɍ��킹�ăC���p�N�g�����߂������̌��t���Ǝv���Ă�����A�������l���������ɂ������B
����́A����l���ߕ߂���������ꂽ���A�ٔ��ɂ���ČY���m�肷��܂ŁA���̐l�͖��߂Ɖ��肵�Ď�舵����A�܂�������咣�ł���Ƃ����̂ł���B���[��A�Ȃ�قǂ��Ȃ�悤���ܒ~�̂��錾�t�ł������B
���ܒ~�̂��錾�t�Ƃ����c�c��
��Q�Q�b�@�w�G�́x
�o��́A���܍��킹�ĂP�V�����ɋÏk���ꂽ�A���E�ōł��Z�����ł���B
�n�삪��r�I�ȒP�Ȋ��ɂ́A�������w�����F�߂��Ă��邽�߁A�L������Ă����B���̒��ŁA�悭����Ȕ��z���ł�����̂��Ƃ��Â��������������̂��B
�w������@��q�̌��́@�V�̐�x�c�c�c�V�̐�̗Y�傳�Ɗ�O�ɂ����q�A�N���������̂��낤�����̌���ʂ��ēV�������ƁA�V�̐�̂��������ʔ��������A���߂Ċ�������B����قǗY�傩�����I�Ȍ��삪���܂łɂ������낤���B
�w��������@�M���̎�@�a�藎���x�c�c�c�Ă̂�����ӂƓ��[������ƁA�Ђ���Ƃ����������i�Ђ܂��j�������z���Ă���B���̒����L�т��s�̐�ɏd�����炭�^���F�̉Ԃ߂Ă���ƁA�Ⓒ���ɂ߂��M���̎p���_�u���Ă���B�����ŁA�v�킸�藎�Ƃ����e�������悬�����̂ł��낤���B����������M���ւ́A�˔�ő씲���A�z�ł���B
���A�z�Ƃ����c�c��
��Q�R�b�@�w�ň����ԁx
�Z�p�҂́A��s�@������ƒė�����Ɗ�����B��������ƁA�ˑR���ꗎ����悤�Ɏv���B�D�ɏ��ƁA���v����ƕs���ɂȂ�B�Ԃ��^�]����ƁA�u���[�L���̏Ⴕ�\������ƍ��o����B�e���r������ƁA�𐁂��悤�Ɏv���B�R���s���[�^�𑀍삷��ƁA�듮����l����B
�Z�p�҂́A�Ȃ����̂悤�ȁu�ň��̎��ԁv��z������̂��B
����v�������̂́A�͌^���g���ċ��x�e�X�g���J��Ԃ����ۂɋ����j���Ƃ�������Ă���B�Ԃ̐v�҂́A�u���[�L�̌��E��m�邽�ߔj��e�X�g��������s���Č����Ȃ��Ȃ�����m���Ă���B�R���s���[�^��������Z�p�҂́A���������ăR���s���[�^�̌듮����o�����Ă���B
���NJJ���҂�v�҂́A�e��̑ϋv��������E������ʂ��āA�ň��̏�ʂ����ی��Ă���̂ł���B
���������āA�������̂�����Ɣ��˓I�ɍň��̏�Ԃ�z�����Ă��܂��B�߂����Z�p�҂̐��ł͂���B�������Ȃ��Ƃ́A���������Ĉ��S�v���Ă���̂ŁA��ɂ����肦�Ȃ��̂ł��邪�c�c�c�B
����Ȃ��Ƃ������c�c��
��Q�S�b�@�w�x
�u���̔�s�@�́A�����X�����傤�ǂɑ�㍑�ۋ�`�𗣗����A�_�ˁA�L���A�啪����ʉ߂��āA�������܌F�{��`�ɖ��������������܂����v�ƁA�X�`�����[�f�X�i�G�A�[�z�X�e�X�A�X�b�`���[�j���@�����������B
�������A���̃A�i�E���X�͂ǂ������������B���ۂ���ȕ���������͂����Ȃ��B����́A�u���������v���ċْ����������q�̎��ɕ������������ł������B
�������Ƃ����c�c��
��Q�T�b�@�w�~�����߁x
��s�@�ɏ��ƌ��܂��Ď�g�Z�����j�[�h������B�~�����߂̒�������g�����̐����ł���B�̂͑S���̃X�`�����[�f�X���A�A�i�E���X�ɍ��킹�Ď��ۂɒ��Ă݂��Ă������A�ŋ߂͓��e�^�̑�^�f�B�X�v���[�ɉf���r�f�I�ő�p����ꍇ������B
�����āA���̐���������u�����A��s�@�Ă���ς肨��������̂��v�ƁA�v���m�炳���B����̓o�X�ɏ���Ė�����h���[�̎g�����̐�������悤�Ȃ��̂ŁA��Ƃ����Ί�ł���A�܂����p�̋��|������q�ɉ������Ă���Ƃ�������B�i����Ɠ������R�œ��掞�ɕ������N����A���̔������̃e���r�̉�ʂɏo��N�ȂȂƎv���ƕ��G�ȋC�����ł���B�j
�~�����߂̒��������Ă������߂ɁA���ۏ��������l������̂��낤���B��s�@�̒ė����̂ŁA�~������������߂ɋ~��ꂽ�Ƃ����l�����l����̂��낤���B
����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A�ЂƂ��틭���V�[�g�x���g����߂��������̍��ł���B
���������̍����狞�Łc�c��
��Q�U�b�@�w�{�Ƌ��x
�Ñ�̂��Ƃ�m��ɂ́A���ɓ`��鎑���ׂ邱�Ƃł���B���R����������Ղ������⋭���邱�Ƃ����邪�A���{�͌Õ����ł���B�����Ďc���ꂽ�Ñ�̕����ɂ́A���R�x�z�҂̂��Ƃ���������Ă��Ȃ��B
���������āA�����͎x�z�҂̏Z�����Ȃ킿�{�a���ǂ��ɂ���A���̋K�͂��ǂ��ł�����������ɂȂ�B
�剤�̏Z���́A���v�V�O�������L�^�Ɏc���Ă���B��Ȃ��̂́A����_���V�c�̓s�Ƃ����u�����{�v�A���̐N������������ɓs���ڂ����u��Ë{�v�A���������ɂȂ��Ē����������̂ł��낤�u�W�{�v�i�����������Ԃ��݂̂�j�A����̓�ɍL��ȋ{�悪�m�F���ꂽ�u�����L��{�v�i�Ȃ���Ƃ悳���݂̂�j�A��a�O�R�̒����ɊJ���ꂽ�u�������v�A ���̒�����^���đ���ꂽ�u���鋞�v�A�i�炭���̓s�ł����������̑S�e�����������u�������v�A��N�̓s�Ƃ��ĉh�����u�������v�Ȃǂł���B
�Ƃ���ŁA�����ł������s�̖��O�ɂ́u�{�v�Ɓu���v�̂Q�����邱�ƂɋC�Â��B�����āA�����͌����č������Ȃ����Ƃ�������B�ǂ��Ⴄ�̂ł��낤���B
�����́A�V�c���Z�����́u�{�v�ɑ��A�u���v�͍c���̉��ɓs�s�v��������s�S�̂����グ���ꍇ�������B�V�O�̒��ŁA���͂킸���ɂU�����Ȃ��B�s�s�v��⌚�݂́A�̂���ς������̂ł��낤�B
���s�Ƃ����c�c��
��Q�V�b �w���������x
���̍c�q�i�݂��j�́A�G���̐�����r���Ƃ������ɂ����B�R�����̒��ɐ^���̕ǁA�ؗ���ɂ߂������̋{�a���A���͋����ēy�ɋA�����B���ĕ����S�����s���������ԁi��������j�����������₩�ȑ�H���A���͍r�ꂽ���a�ɂȂ����B
�����̒n�ʼn��������ޑ�a�O�R��]�݁A�J�s���h���ɂ߂铡���̋{������ɂ��A���������������̒n�̎₵�������݂����Ă���B
�{���Ɏd���鏗�������̛g�����₦�ċv�������A�ڂ��ނ�Δޏ���̎p�������ɂ���B���̒�����₩�Ȗ������������͐̓��ƕς炸�A���̑���h�炵�Đ��������Ă���
�B
�u�я��T�@�������@���������@���s�������@���p���z�v �i���˂߂́@���łӂ����ւ��@�����������@�݂₱���Ƃ��݁@�����Â�ɂӂ��j�v
���̎u�M�c�q�̎��ɁA��ȉƑ�q�Y�����s��ȋȂ������B���{�×��̋Ȓ��ɁA�������̐̂��Â�閼�Ȃł���B
���̉̂𖾓����ɂ���`�W�{�Ղŕ������Ƃ��ł���B�i�������̋��Ղŕ�����e�l�����ɂ�藬����Ă���B�܂����̉̂́A���t���s�̂��莁�̉��t�ł����錢�{�F�搶���D��ʼn̂��Ă���B�j
�����Ƃ����c�c��
��Q�W�b �w���ׁx
���͂قƂ�Ǖ��ׂ������Ȃ��B���ׂ��Ђ��ĔM���������L�����Ƃ�ƂȂ��B�P�O�N�Ɉ�x�A�����M���ł����ł���B
���������āA��Ђ͕a���������Ƃ��Ȃ��B����x�݂����鎞�ł��u������ƔM�ۂ����āv�Ɛ�o���킯�ɂ͂����Ȃ��B���ׂ������Ȃ��Ǝ���ɐ錾���Ă���̂ŁA���̎�̌�����͒ʂ��Ȃ��B
���ɗւ������ď�v�Ȃ̂��A�N�ł���B�ޏ����M���������̂������ȗ��������Ƃ��Ȃ����ŕa�����L�����Ȃ��B������ƕ@�������������鎞�͂���悤�����A�Q�����Ƃ͂Ȃ������B
����ȓ���̎��̕v�w������A���̎q��l�͕��ׂɑ��Ċ�̂悤�Ɋ��ł���B���ׂ��Ђ��ĐQ�����Ƃ��Ȃ��i�������Q��͕̂��ׂ������Ăł͂Ȃ��A�z�c�������Ăł��邪�j�B
���ꂪ�ǂ������Ƃ����邩���m��Ȃ����A�Ƃɂ������̉Ƒ��͕��ׂ������Ȃ��B���Ƃ����Č��N�Ƒ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�Ƃɂ������������ɂ͂߂��ۂ������̂ł����B
�ᑱ���Ă������c�c��
��Q�X�b �w�������̖@���x
���́A�O�q�̂悤�ɂقƂ�Ǖ��ׂ������Ȃ��B�������ׂ̋ۂɑ��������̎��ł��邩������Ȃ����A����ȏ�ɕ��ׂɑ��邠�邱�Ƃ����s���Ă��邩��ł���B
����́A���w�Z�ŏK�����g���ׂЂ��̖@���h�ɒ��ӂ��邱�Ƃł���B���̖@���Ƃ́u���ׂ̓`�����́A�����̂R��ɔ���Ⴗ��v�Ƃ����g�藝�h�ł���B����́A���������ɂ��R�������̌����ߖ��Ƃ��ďo�肳�ꂽ�̂ŁA������������Ɖ����Ă���B
���ׂ������Ă���l�ɋ߂Â��߂Â��قlj���₷���Ȃ�A���̊m���͂P���̋������P�Ƃ���ƁA�T�O�����Ȃ�Q�̂R��̂W�{�ɂȂ�Ƃ����̂ł���B�N���������Ċm���߂��̂��A�{���ɂR�悪�������̂��A�l���͂Ȃ��̂��Ȃǒ肩�łȂ����A�펯�I�ɂ͕��ׂ��������l���牓���ɂ���������S�ł��낤�B�����Ŏ��́A���ׂ������Ă������Ȑl������ƁA������u�����Ƃɂ��Ă���B����ő����Ƃ����ׂ������Ȃ��ł���悤�Ɏv���Ă���B
���͂��ĕ��ׂ���������Q�̂��Ƃ����s���Ă����B��́A�g�ƂɋA�����炤����������h�ł���B���������ׂ̋ۂ��@��A�̔S����ʂ��đ̓��ɓ��荞�ނ̂͐ڐG���ĂP�O���ł��邱�Ƃ�m��A�ƂɋA���Ă���̂������͈Ӗ����Ȃ����Ƃ�������~�߂ɂ����B
������́g�~�ɔ���������h���Ƃł���B�l�̎葫�͋C���Z���T�[�ŁA�����Ŋ�����������ƁA�厖�ȑ���̂��鋹���ƕ�������낤�Ƃ��đ̉����グ��B���̂��ߔ����ł́A�̉���������ȏ�ɔ��M������B������ׂ̋ۂ��̓��ɓ���ƁA�͉̂��w�����𑣐i�����ċۂ��E�����Ƃ����̂��ߑ̉����グ�邪�A���ꂪ���M�ƂȂ�B����Ɠ�����R�͂̂����Ԃ��A�������邱�Ƃō�낤�Ƃ����̂ł���B������������̂͌��ʂ�������������Ȃ����A��g�[�������Ă��鍡�ł͈Ӗ����Ȃ���͂�~�߂Ă���B
���Ǖ������Ή��R�����̂����A�������s���Ă���̂́A�g���ׂ������Ă���l����ł��邾�������������h���Ƃ����ł����B